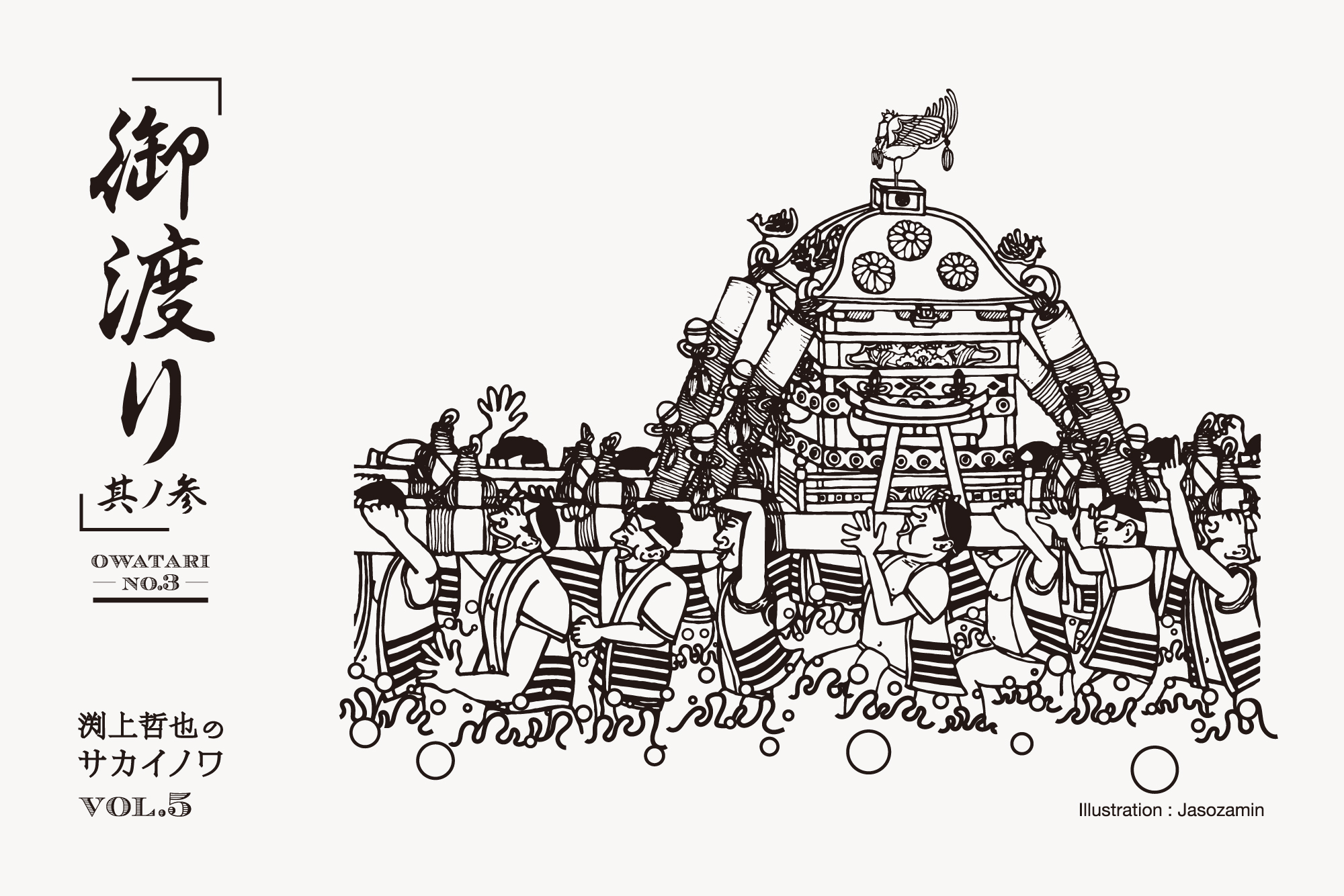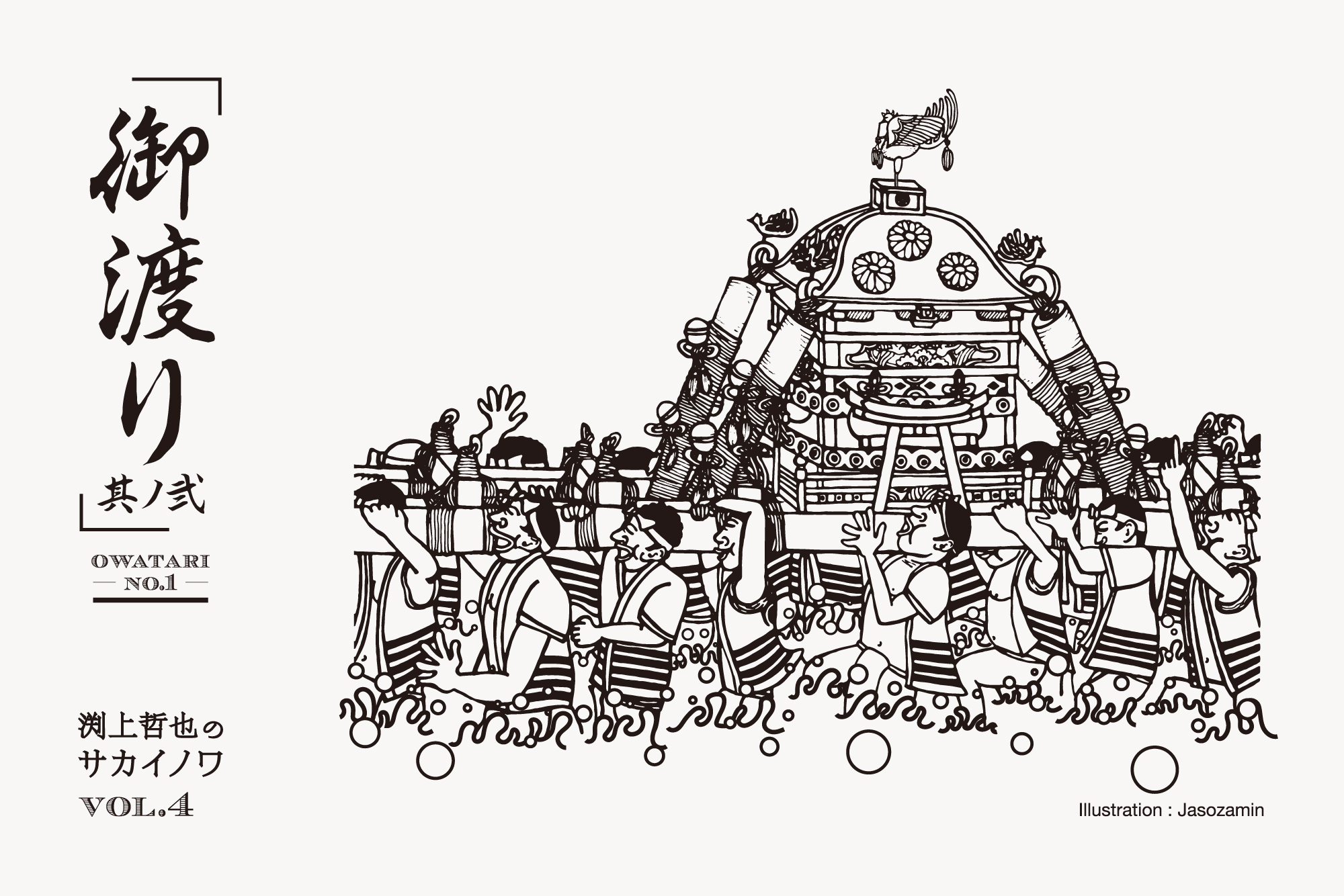STYLE 過去・現在・未来の様々な視点で堺の持つ魅力を発掘/検証/企画/提案

REPORT
SAKAINOMA talk vol.1 ゲスト中嶋弓子さん
2022年7月22日の夜、SAKAINOMA cafeにてトークイベントが開催されました。名付けて「SAKAINOMA talk」。
ゲストは、日本財団の職員で、書籍『難病の子どもと家族が教えてくれたこと』を出版された中嶋弓子さん。サカイノマオーナーの先輩というご縁で、今回このような機会が生まれました。

アメリカナイズされてるね!
たいていのトークイベントでは、「コホン、それでは時間がきたので始めます」といったようにかしこまってスタートすることが多いけれど、この日は違う。会が始まる前の雑談タイムの延長線で、いつの間にか本編に突入していた。
中嶋さんはとにかくニコニコしていて、ペラペラしゃべる。日本人が日本語を流暢に話すなんて不思議でもなんでもないはずなのに、なんだろう、彼女は身体全体を使って水が流れるように話すのだ。手のひらをしなやかに回転させる仕草や、ちょっとしたジョークを時折交じえながら、聴衆を中嶋ワールドに吸い込んでゆく感じだ。

その不思議な魅力は、彼女の生い立ちを聞いて納得した。生まれは京都、育ちはアメリカ。いわゆる帰国子女なのだ。どうりで異色に感じたわけである。
異色といっても決してネガティブな意味ではない。「You、アメリカナイズされてるね!」といった、明るくてユニークな感じ。彼女自身も「私こんなんだから、日本財団でも浮いてるの」とケタケタ笑う。
そうかと思えば、みんなが心地よく居れるよう、細やかな気遣いも垣間見せる。そのホスピタリティの所以は、数多くの難病の子どもたちとの触れ合いに由来しているのかもしれない。

「あたりまえ」「普通」ってなんですか?
中嶋さんは、日本財団の職員として、難病の子どもと家族を支えるモデル施設を全国に30か所整備してきた。著書『難病の子どもと家族が教えてくれたこと』には、これまで出会った多くの難病の子どもやその家族、そして、その家族を支援する支援者たちとの交流を通じ、どのようにモデル施設の整備を進めたのかについて書かれている。

小児がん、筋ジストロフィー、ダウン症候群といった病名は誰しも聞いたことがあるだろう。こういった「難病」を抱える子どもの数は、全国に25万人以上。ただし、これは国が指定する788疾病に関する数字にすぎない。難病の申請をしていない、したけど指定されていない子どもが存在することを忘れてはいけない。
ところで、25万人ということは、日本人口の0.2%にあたる。そんなマイノリティの彼らが「あたりまえの暮らしがしたい」「普通の子どもの暮らしがしたい」と言うと、私たちはつい、いわゆる「健常者」の暮らしをあてはめてしまってはいないだろうか。
でも、それは時に不正解であると中嶋さんは話す。一口に「難病」といってもさまざまだし、たとえ同じ病気であっても、症状や環境など個別具体的な事情によって「あたりまえ」「普通」というものは異なってくるからだ。
自分にとってのあたりまえが、誰かにとってはそうでなかったり、自分にとっての普通が、誰かにとっては難しいことだったり。ステレオタイプの考え方や自分のモノサシで決めつけず、目の前にいる人に寄り添い、その人にとっての「あたりまえ」や「普通」が何かを考えてみることが大切だ。
そんな話を、「私浮いてるの!」という中嶋さんから聞くからこそ、なんだかやたらと説得力があった。
問題はバリアフリーじゃない
中嶋さんは、重度の身体的障がいを抱えている子どもの家族の話もしてくれた。
彼らは、家族全員で旅行にいったこともなければ、家族と一緒にお風呂に入ったこともない。お出かけしたくても、施設から対応できないからと利用を断られることが多い。以前よりバリアフリーが進んできているとはいえ、まだまだ課題は多いのだ。

しかし、一番の問題は、実はそこではないのだという。たとえ建物の構造や施設の体制的に受け入れができるようになったとしても、彼らには家族でお出かけできない理由がある。
それは、人の目が怖いということ。
いくらバリアフリーが進んでも、人の考え方が変わらなければ、彼らはいつまでも外へ出ることができない。それを知って、私たちはどうしていくべきだろうか。どうしたら、彼らが家族と一緒にお出かけするという、私たちにとって「あたりまえ」のことを気兼ねなくできるようになるだろうか。
楽しくないと寄付しない。
最後に、難病の子どもの支援だけでなく、300団体を超える非営利組織に対し、資金調達の支援も行ってきた中嶋さんは、寄付の在り方についてこう話してくれた。
「楽しくなきゃ、寄付なんてしないから」
5歳からアメリカの寄付文化にどっぷり浸かってきた中嶋さんのこの一言は、まさに日本の寄付活動の課題を言い当てているように思う。

この日集まった人の中には、社会福祉法人やNPO法人の運営に関わる人も多く、それらの事業は、誰かの人的、物的、あるいは金銭的支援のもとに成り立っているケースがほとんど。
私もそのひとりで、NPO法人の運営上寄付を募ったこともあれば、クラウドファンディングの仕事をしたこともある。その経験から日々感じていたことは、「ガラスのハートじゃ寄付なんて募れない」ということ。寄付を募るのは、思ってる以上に精神的に疲れるのだ。
でも、中嶋さんの話を聞くと、もしかしたらそれは日本人特有の悩みなのかもしれないと感じる。寄付には真剣さや必死さはもちろん必要だ。が、それだけでは寄付を募る方が精神的に疲れてしまうし、賛同も広がらない。
プロジェクトがユニークで、「寄付しようよ!」「えっしないの!?ジョインしないなんてもったいない!」といったアメリカナイズされたノリで寄付を募ることができれば、寄付がより身近なものとなるのではないだろうか。そして、誰かの犠牲のもとにではなく、みんなの笑顔の先に社会課題の解決が待っているのではないだろうか。
そんなことを考えさせられた夜だった。
彼女に興味をもったら、ぜひこの本を読んでみてほしい。難病の子どもがいてもいなくても、考えさせられることがたくさん詰まっているはずだ。

『難病の子どもと家族が教えてくれたこと』(クリエイツかもがわ)>>>